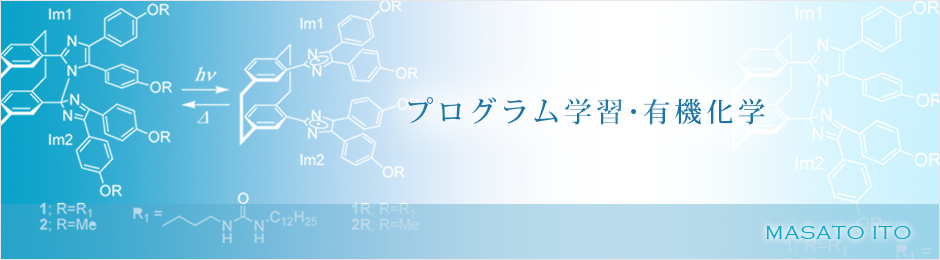1.6 立体構造の表示法
1.6 立体構造の表示法
1つの分子式に幾つもの異なる分子が対応するとなると、化合物の命名法は重要な役割をになうことになる。第一に1つの化合物名は必ず1つの化合物に対応しなければならない(1つの化合物が2つ以上の名称に対応することはある)。第二に化合物名からその構造が誰にでも正しく再構成されなげればならない。ラボアジエの時代からこのかた、化学者は合理的、普遍的でしかも簡便な命名法を確立するために、なみなみならぬ努力を払ってきた。その結果、比較的簡単な化合物の名称は、初心者にも理解し、利用できるものとなってきた。たとえば、C4H9OH(表1.6.1-2~5)の名称は以下のようである。

表1.6.1
第一の命名法(A)は、19世紀から用いられている伝統的、慣用的なものであるのに対して、第二の命名法(B)は、より規則的、系統的であり、原則をのみこんだ後は(B)のほうが利用しやすい。
構造式は等しいが原子の空間的配置が異なる立体異性体に対しても、第一に1つの立体構造と1対1で対応し、第二にその名称から立体構造が再構成できるような命名法が必要である。分子の立体化学をも含む命名法、すなわち立体化学命名法は、化合物命名法よりもはるかに歴史は新しいが、その発展のパターンはきわめて類似している。すなわちまず最初にある特定の化合物群(たとえばアルケン、オキシム等)に対する立体化学命名法(慣用的命名法に相当)がつくられ、その後すべての化合物群に適用できるような系統的命名法が考案された。
ゆくゆくは後者の命名法に統一される傾向にあるとはいえ、前者の命名法も知らないわけにはゆかない。現実に両方の命名法が用いられているし、さらに古い命名法で書かれている過去の文献の必要性もまだまだおとろえないからである。そこで、本書でも必要に応じて両方の命名法を学ぶことにする。
【順位規則】
系統的立体化学命名法の基礎に順位規則(sequence rule)がある。順位規則によって一群のリガンドの間の優先1頂位が定まる。
順位規則によって定められた順位、および各種化合物のそれぞれに関する2、3の規約によって立体化学が記述される。順位規則を説明するために、化合物19の原子Xに結合している4個のリガンドの優先順位をつけてみよう。

図1.6.2
【優先順位の決め方】
- 原子は一般に原子番号の大きいものが原子番号の小さいものに優先する。
- 同位体の中では、質量数の大きいものが質量数の小さいものに優先する。
- まず第一に直接結合している原子(P、Q、A、A)の間で比較して優先順位をつける。
- 同等の原子(A、A)があるときは、それぞれに直接結合しているリガンドを優先順に並べたもの(B、C、D)を、もう1つの原子の持つリガンドを優先順に並べたもの(B、C、E)と比較する。
- それでも順位が決まらないときは、この操作を順位が決まるまでくり返す。
- 二重結合や三重結合のある場合は、あたかも2本の単結合があるかのように扱う。すなわちA-B二重結合においては、A原子は1個でなく2個のB原子と、同様にB原子は2個のA原子と結合しているとして1~5の規則を適用する。

図1.6.3
このような(A)原子、(B)原子をレプリカ(replica)原子という。
S1.5にはよくでてくるリガンドを、優先順位の低いほうから順番に列挙した。この順位は置換によって容易に変動するので注意を要する。たとえばメチルCH3-はエチル-CH2CH3より低位であるが、フルオロメチル-CH2Fはエチルより高位である。