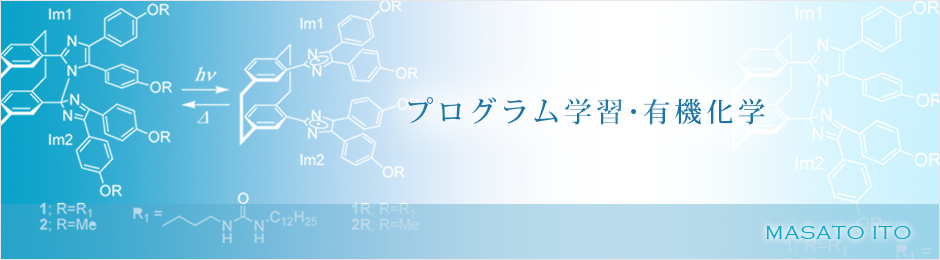1.1 異性・異性体
1.1 異性・異性体
有機化合物にしても、無機化合物にしても、1つの化合物には1つの分子式が対応する。しかしその逆は必ずしも正しくはなく、1つの分子式に2つ以上の分子が対応することも少なくない。分子式は等しいが構造の異なる分子は互いに異性体(isomer)であり、このような現象を一般に異性(isomerism)という。異性体どうしがどの程度互いに類似しているかによって、異性にもいろいろ種類がありうる。ゆえに異性を理解するためには、まず個々の分子の分子構造を正しく定め、表現することが必要である。分子式(molecular formula)は1つの分子の中に含まれる原子の種類と数を示す。
示性式(rational formula)は、分子の特徴的な性質のもとになっている部分、すなわち官能基(functional group)を分子の中でまとめて書き、その化合物がどのような化合物群に属するかを明示する。構造式(structural formula)では、原子と原子を必要な数の価標で結びつける。これによって、原子の結合順序という範囲での分子構造ははっきり明示される。

図1.1.1
構造式2~5(図1.1.1)において、C-C結合、C-O結合、C-H結合、O-H結合のそれぞれは長さが異なっているが、構造式において価標の長さを特に結合の長さに対応させる約束はない。また1つの原子から2本以上の結合が出ている場合、それらの結合がつくる結合角についてもそれらを構造式に表わすことはしない。たとえば、実験的に求めた水H2Oにおける結合角∠HOHは約104°である.しかし水の構造式としては通常図1.1.2-6あるいは図1.1.2-7のように書く。構造式では、価標の長さや方向が分子構造に正確に対応しているわけではない。

図1.1.2